
web,ホームページの作り方
web,ホームページを作るために必要な知識と注文するために知っておきたい事柄です。
インターネットを活用するときに自社ホームページだけでなく様々なweb広告やSNSでバナーは必要ですね
単純明快なほうがよいですね。じっくり読んでもらうことよりも瞬間のインパクトの方が重要です。
パッと見た目でわかりやすいものが向いています。図法だとしたら見た目がカラフルで見やすいものがいいですね。
会社名のロゴがバーンと来るものもあります、色使いはゴチャゴチャしないほうがよさそうですね。
広告媒体によって指定のサイズが決まっています。元のバナーを大きめに作っておいて、様々なサイズに対応させることもできます。
web広告だけではありません。自身のブログのヘッダ画像だったり、iTunesやamazonnなどで音源配信をする場合などもCDジャケット相当の画像が必要だったりプロフィール画像が必要だったりします。スマホに入ってるお気に入りの写真を使えばいいのですが、加工したり文字を追加したり合成したりすると見栄えがよくなります。

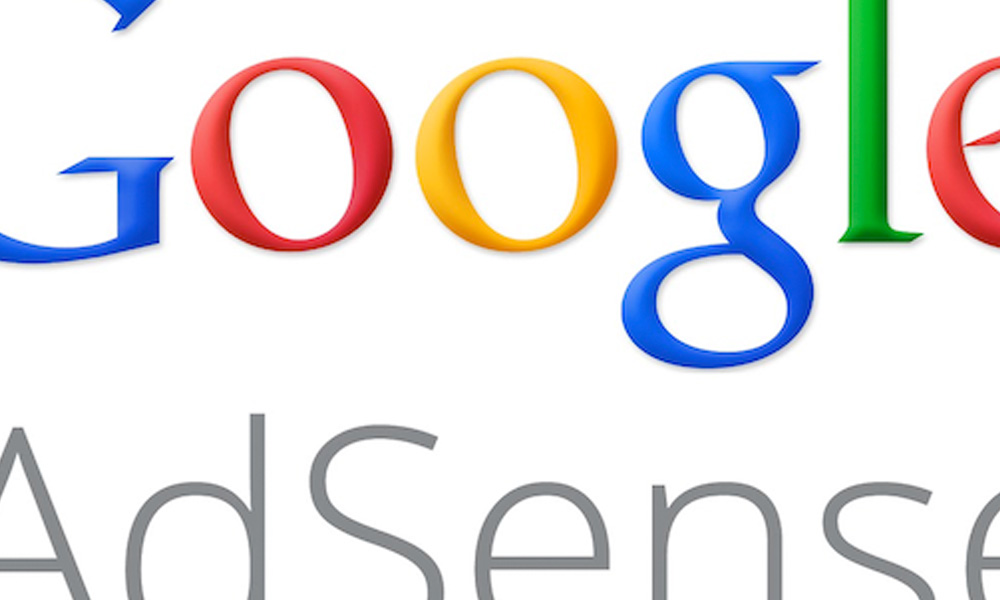
Googleの広告配信プラットフォームです。よくありそうなのがこの5サイズでしょうか。
などなど。こちらをご参照下さい。

Facebook、Instagram、Twitterなど
アスペクト比: 1.91:1の場合、1280×670px、1200×628px
アスペクト比: 1:1 の場合、600×600px、1200×1200px

ここまでは広告についてのサイズになります。出稿に関する詳細はそれぞれ広告出稿先にてお問い合わせしたり申し込んだりしてください。
有料の広告以外にも自分のブログやFacebookのイベントなど様々なシーンで画像バナーが必要になります。それぞれ必要なサイズを調べてみて独自のバナーを作ります。
またイベントなどでチラシ、フライヤーを作るかわりに記事にアップする画像も作ることがあります。その際のサイズは自由ですが、大きめで作るとキレイに見えます。

様々な音源配信サイトがありますが廷々下記のようなものが必要です。
ファイル形式: JPG、PNG
ファイルサイズ: 20MB以内
画像サイズ:(小)800x800px、(大)3000x3000px
がCDジャケットの代わりになる画像です。それぞれの音源配信サイトによって多少のばらつきがあるのでチェックしてください。また当然ながら著作権にひっかかる画像は一切使えないので注意です。
Photoshopとかそういうものです。レイヤー機能があっていろいろな素材を重ねて合成したりします。画像サイズや画像解像度をちゃんと設定できるものじゃないとだめですね。また保存の形式がJPGやPNG、GIFなどで保存できるものです。
瞬間的に読ませたい文字を、極力文字数を削って大きくするとよいと思います。直感でなんの宣伝かがわかるといいですね。商品となる画像がメインになるのか商品名がメインになるのか、はたまた会社名などがメインになるのか、目標をきっちり決めることが大事です。
とにかく派手なら目立つのか、というとそうでもないですね。ごちゃごちゃして何か分からなかったら意味がないです。また目標とするターゲットに響くかどうかもわかりません。どういった人たちにどのような雰囲気を与えるのかを考慮して見やすいシンプルな画像にします。
いかにも広告宣伝ですっていうのがいいかどうかはわかりませんが、どういった人々に見てもらいたいのかは決めた方がいいですね。それによっておもしろ系にするのか、ゴージャス系にするのか、またはお悩み系にするのか、でベースのデザインも決まってきます。
もしもそのバナーをクリックした場合、どこへ飛ぶのでしょう?特定商品ならそれ専用の特設サイトでしょうか。自社のオフィシャルサイトでしょうか。せっかくクリックしてもらうんだからその受け入れ先もちゃんとしておかないと取りこぼしちゃいますね。

たぶんググればなんかいろいろ出てきますよ。どれがどうだとかはわからないので実際インストールして使ってみてください。
きっといくつもいくつも時間をかけて作ればなんとなくそれっぽいものが出来るようになる(はず!)です。

本来の業務があるのにバナー作りに時間をかけられない、また今更そのために新しいソフトの使い方を覚えてる余裕はない、という場合はもう外注ですね。バナーひとつくらいならそんなに高額ではないと思います。
仮に制作費が1万円だとしたらご自身の手間と時間と本来の業務に与える影響を考慮して高いか安いか判断されたらよいでしょう。